コロナは、障害者の蓄積を逆戻ししかねなかった
――熊谷先生は医師でありながら、ご自身にも重度の身体障害があって、介助を受けながら生活をされています。またこれまで、障害者などの当事者研究においては、理論と実践の両面で多くを積み上げてこられました。2017年度からは東京大学のバリアフリー支援室の室長も務められています。
このインタビューが、今回の一連の取材の締めくくりになるのですが、今日は障害当事者として、また医師や支援者というお立場として、そして当事者研究の視点からもお話をお伺いできればと思います。
熊谷 わかりました。それではまず、私自身が障害当事者としてどうコロナ禍を経験していたかお話ししたいと思います。
このコロナによって、社会モデルで言う障害、つまり私の体のコンデイションの方ではなくて、環境とのミスマッチという意味での障害が増えた場面と減った場面の両方があったと思います。
まず減った方はなにかと言うと、例えば移動しなくてよくなったことです。私の場合、移動中の快適性がとても低く、乗り物酔いもしやすかったので、これまで移動時間をずいぶん無駄にしていました。それがなくなっただけでも楽になった。あとちょっとマイナーな喜びとしては、アクセシビリティの理由でこれまで行けなかった飲食店が宅配を始めたことで、向こうからこっちに出てきてくれるようになった。
一方で、深刻なミスマッチがありました。介助の問題です。特に身体ケアは三密を避けられないので、いわゆる多数派の人間像を基に設計された感染症対策は通用しませんでした。特殊な介助という人間関係の場面における感染症対策のポイントを、自分たちで考えなければならなかった。例えば、自宅に来て介助をしてもらっていいのかといったことも、情報が全くなかった当初は非常に迷い、すごく敏感になっていました。徐々に様子がわかってくると対策の取りようもあるとわかってきたのですが、特に昨年上半期くらいはどうしたものかと考えていましたね。
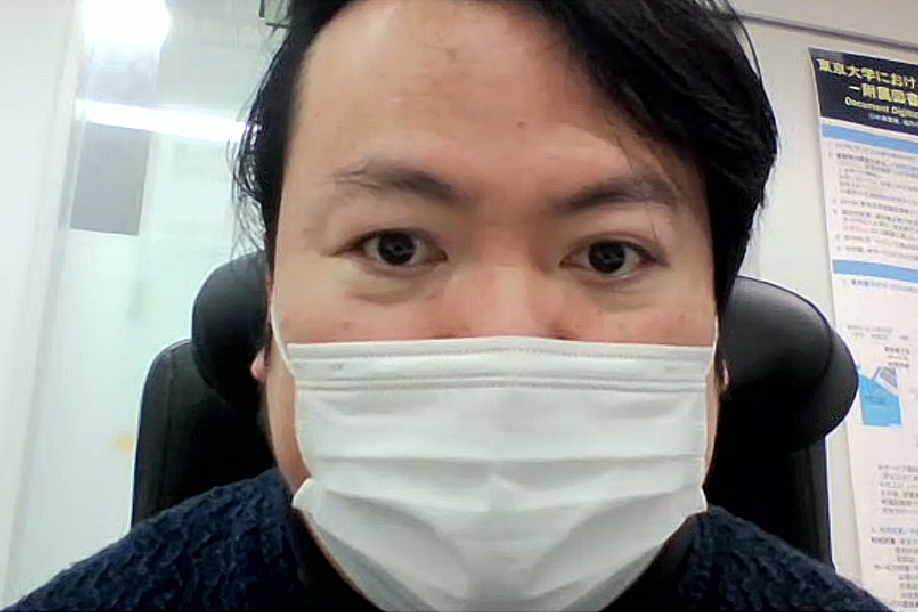
――介助者に来てもらえないと生活ができなくなるわけですが、どうされていたのでしょうか。
熊谷 結局初めの頃は介助者によるケアの量を減らして、その結果、家族にケアを頼む割合がすごく増えてしまっていました。これは私にとっては非常に大きな出来事です。私のように重い障害をもっている人からすると、頼れるのが家族や一部の友人だけというのはすごく危ない状況なんです。なぜかと言うと、その家族や友人の体調が悪くなったり環境が変わったりしてケアができなくなった瞬間、私の生活も継続できなくなるからです。
あるいは善意や愛情をベースにした介助関係では、その人との関係を良好に維持し続けていなければ、私が介助を受けられなくなるという状況にもなります。そうなると、どうしても自分のニーズを後回しにして、相手のペースに知らず知らずのうちに合わせていくような、そんなライフスタイルになし崩し的になっていきますよね。その延長線上には、悪気はなくても、支援する側がペースを握ってしまう権力関係みたいなものが出てきてしまう。
これは介助をする側からしても問題があって、自分一人に全ての責任がのしかかるのはすごくストレスのかかる状態です。介助だけで一日が終わってしまう。仕事もできない、自分の時間がもてない。そうなると、その人自身のチャンスがどんどん奪われていき、疲労も不満も蓄積していきます。
こういう状況に置かれたケアの人間関係は、一触触発というか、いつ暴力的な関係やネグレクトの関係になるか分からない。高齢者介護や育児というケア領域でもそうだと思うのですが、とにかく一部の人にしかケアが頼めない状況は危ないというのが先輩の障害者から脈々と受け継がれてきた知恵でした。
ところがコロナは、それを逆戻ししかねなかった。かつて30人とか40人いた介助者が、1人とか2人になってしまう時期が去年の夏ぐらいまでありました。徐々には戻ってきましたが、とにかく「依存先を増やす」ことをこれまでやってきたのに、それが突然失われたわけです。
――取材をした障害当事者の中には、もしも自分が発熱したら支援者は来てくれないんじゃないか、病院に行くことすらできないんじゃないかと、とにかく不安になって、それで最終的には家族に頼るしかないと考えていた人もいました。でも家族に頼れる自分はまだ良い方で、それができない人もたくさんいると話していました。まさに#3で話を聞いたブックマン・マークさんは、アメリカにいる家族に頼ることも、ご自身が帰国することも許されない状況で、大変なことが集中しているように思いました。
熊谷 本当にそうですね。こんなに隣の人たちがどういう苦労を抱えているのか分からない状況って、今までなかったと思います。全く異なる障害が発生しているかもしれないのに、隣の人が気付かない、分離されてしまっている状態でした。
インフォーマルな情報へのアクセシビリティ
――あるカウンセラーの方が、自分もコロナ禍を体験した当事者として、クライアントが訴えるコロナ禍の苦しさに簡単に共感してしまいそうになるんだけれど、それはすごく危ないんじゃないかと言っていました。本当に同じ苦しさや大変さを経験していることなんてなくて、そこを分けて考えなければならないと。感じている苦しさや大変さは、同じようにみえて実は違っていたのではないかということです。
熊谷 よくわかります。私も支援者の立場として、あるいは小児科医として、まず相手の状況が「わからない」というところからスタートしました。自分のことさえよく分からなかったので当然なのですが、みなさんが何に困っているのか本当によく分からなかった。
確実に4月以降、相談に来る方の顔ぶれが変わり、内容も変わっていきました。そうした中で、徐々に、どうやら障害の分布みたいなものが変わりつつあるんだなと感じ始めました。
例えば授業に参加し難かった学生が、オンライン授業になったことで参加しやすくなったり、横になりながらでも授業が受けられる状況になった。これは本当に良かったことで、コロナが過ぎ去った後でも、オンラインの選択肢は残した方がいいと思います。
その一方で、思いもよらなかったことがありました。例えば集中を持続することがより困難になり、状況が悪化したケースです。教室という空間は、インフォーマルな「集中アシスト」みたいなものを可能にするインフラがいろいろと張り巡らされていたんですね。今になってよく分かったのですが、ピア・プレッシャーと言いますか、隣の学生が集中しているから、そのプレッシャーを感じて自分も集中できるとか、あるいは教師がいつ当てるか分からないから集中が持続するといったインフォーマルな集中アシストが存在していたわけです。それがオンラインになるとなくなってしまうので、授業に集中し続けることができなくなった。
――自分自身の実感としても、とてもよくわかります。コロナの前までは当然過ぎて、わざわざ考えなかったようなことかもしれません。
熊谷 今になって、この「インフォーマル」というのが非常に重要だったことがわかってきました。同じ教室に集まれば、試験対策の話とか、「この辺がヤマだよ」とか、過去問の情報とか、雑談のレベルで様々な情報が飛び交っていた。大学側も、もしかすると無自覚にそこに依存していたかもしれなくて、インフォーマルなネットワークの存在があって初めて単位が取れるようにデザインされていた側面があったと思います。
――確かに学生は以前のようにはつながれなくなっていったのですが、それでもいつの間にか新入生がLINEでつながっていたり、会ったこともないのに横のつながりができていたりして、なんだかんだうまくやれているように思える状況もありました。けれども、そこにはどうも暗黙のルールがあるようで、馴染めない学生がいたり、そもそもLINEグループの存在を知らない学生なんかもいて、これまで以上につながりにくい状況が生まれていているのではないかという話もありました。
熊谷 それに似たことはこれまでもあって、多数派のコミュニケーションの様式と体の相性が合わない人たちはずっといました。私は自閉スペクトラム症を、本人のコミュニケーション障害ではなく、多数派のコミュニケーションスタイルとのミスマッチと定義しています。
今回は特に、雑談的なコミュニケーションスタイルが体に馴染まない人にとって、インフォーマルな情報のやり取りへのアクセシビリティの問題が、より一層深刻になって現れていたのかもしれませんよね。これらは私自身想像もしていなかったというか、後付けで解釈できるにせよ、事前に予測できなかったことです。
文化的障壁をどう取り除くか
――インフォーマルな部分の重要性はわかるのですが、そこに支援みたいなことって考えていくべきなのか、それともそこには支援なんて考えられないのか……。
熊谷 難しいですね。聴覚障害がある学生にも、発達障害や精神障害がある学生にも関係することですが、フォーマルな情報保障の方はずいぶんと方向性がみえてきた気がします。ですが、インフォーマルなやりとりに関しては、例えばお昼休憩やサークル活動の情報保障をどうするかといったことは、まだはっきりとはみえていませんよね。
本来は、そうした活動も大学のキャンパスライフを構成する重要な要素で、フォーマルな情報保障や支援だけをすれば十分と開き直れないはずです。ただ、どういうふうに支援の制度設計をしていけばいいのか、私自身もまだわかっていません。
――インフォーマルな部分にも支援をしていくとなると、その弊害と言いますか、大学の介入度合いが大きくなっていって、少し変なことにもなりかねないなという気もします……。
熊谷 そうなんですよね。少し視点を変えて考えてみると、このインフォーマルな部分というのは、カルチャーのレベルの話でもあって、最近私が考えている「構造と文化」という区別から考えることができるかもしれません。
構造とは、建物や道具、ルール、仕組みといった、文章も含む「モノ」で表現される統治システム、コントロールのことです。一方、構造ではなく、文化によるコントロールのシステムもあります。文化は、人々の価値観や慣習、あるいは態度やコミュニケーション様式といった、「ヒト」に宿る、モノとして取り出せないものです。
ダイバーシティやインクルージョンの話でもそうなのですが、構造へのアプローチだけでは不十分で、文化へのアプローチがどうしても必要になります。これは障害以外のダイバーシティの領域では散々言われてきたことで、例えばジェンダーやエスニシティの問題などは、制度のみならず人の心や考え方といった文化の問題にも目を向ける必要があると主張されてきました。障害者権利条約の中にも、障壁の例として「態度(attitude)」があげられていますが、それもやはり障壁というのが制度や物理的な構造のレベルだけじゃなくて、文化的なものでもあるということなんです。
インフォーマルなコミュニケーションから疎外されている状況は、構造的障壁というよりは文化的障壁と言えるでしょう。ですので、それを取り除く戦略というのは、例えば差別やスティグマを減らすアプローチに近いものになると思われます。アクティブ・ラーニングやゼミ、当事者同士のサークルといったところに実際に出向いて対話をするとか、そういった形で人々が考えたり対話をするようなアプローチが必要なんじゃないでしょうか。
支援の枠組みとして、文化にアタックすることは避けられないと思うのですが、障害の領域はどちらかというと、これまで構造にウェイトが置かれていた感じがします。もちろん、構造的スティグマという概念が教えてくれるように、構造と文化は相互に影響を与えあっていることは論を俟ちませんので、構造が重要ではないという意味では決してありません。
今求められていること
――インフォーマルなやりとりが失われ、さらにディスアビリティが変化したことで、自分が今まで困っていたこととは違う、例えばオンラインゆえの困りごとが新たに生じていたわけですが、これまでにない状況に直面した学生たちが、困っていることにうまく気付けず、かつ相談にも来れなくなったということがありました。
熊谷 そうですね。コロナに限りませんが、障害というのは自分の体が変化したことによるミスマッチと、自分の体は一ミリも変化していないけれど、社会環境の側が変化したことにより起こるミスマッチと両方があるわけです。今コロナによって社会環境の方が一ミリどころではなく、急激に変化をしていますから、ミスマッチが普遍化されて、いわば障害が普遍化された状況があると言えます。
自分の体に明らかに平均とは違う体の特徴がある当事者は、なんとなくミスマッチが起きるだろうということがわかるし、周りも気付きやすいですよね。ですが、ぱっとみたところ、自分の体には平均と違う場所が見当たらない人とか、わかりづらい人は、まずこのしんどさが自分の努力不足なのか、それとも環境を変えてもらわないといけないケースなのか、そうした区別すらも曖昧になるわけです。ですからみんな、コロナ禍で困っていることが自分のせいなのかとか、私は甘えているだけなのかとか、あるいは過度に環境が全部悪いみたいな思考になってしまうことが、仕方ない状況になっている。
そうしたことを乗り越えるノウハウとして、これまで自助グループという実践がありました。自分のみえにくい困難をみえる化していくプロセスというのでしょうか。ですから潜在的には自助グループの集まりがすごく必要だと思うのですが、それが今コロナでできなくなっていて、より困難な状況に置かれていると思います。
――今、人が集まって話をすることが本当は求められていると。
熊谷 障害者だけじゃなくて、「困難を抱えた人々」という意味では、現状、実はあらゆる人が当事者になったと考えていいと思います。当事者同士が集まって情報交換をしたり、お互いの置かれている状況を比較したり、密に情報をやり取りして一緒に考える作業が今必要なはずです。
コロナ以前から、そうした当事者による集まりによって生き延びられてきた人たちがいました。特に依存症でしんどい思いをしている人たちが、毎週毎日のように一緒に自助グループに通って、ようやく、薬物やアルコールを過度に使わずに済む状況を維持できていたわけです。障害をもっている人もそうですが、困ったときほど集まることが大事だった。
今は健常者も当事者になっている状況ですから、集まることが断たれたというのはすごく大きなことです。そのことによって、自分の抱えている困難を、全体の布置の中でどう捉えるのかがわからなくなっている。私だけの話なのか、よくある「あるある話」なのか。「あるある話」だったらほっとするみたいなことがあったわけですよね。そういうことがわからなくなったことが、今回の大変さに拍車をかけているように思います。
後編につづく
熊谷晋一郎・くまがやしんいちろう
1977年、山口県生まれ。新生児仮死の後遺症で脳性麻痺になり、以後車いす生活となる。東京大学医学部医学科卒業。東京大学先端科学技術センター准教授、小児科医。専門は小児科学、当事者研究。主な著書に、『リハビリの夜』(医学書院)、『当事者研究―等身大の〈わたし〉の発見と回復』(岩波書店)、綾屋紗月氏との共著に『発達障害当事者研究―ゆっくりていねいにつながりたい』(医学書院)、『つながりの作法―同じでもなく 違うでもなく」(NHK出版)、國分功一郎氏との共著に『〈責任〉の生成―中動態と当事者研究』(新曜社)など、多数。