誰にとっても配慮は必要
――おっしゃるように、全員が当事者になった状況が生まれ、みんなにとって今こそ自助グループのような集まりが必要だと言うのはその通りだと思います。
そのことを少し支援の点から考えてみたいのですが、障害はないけれども、いわゆる「健常者」だけれども、ディスアビリティとしての障害を経験している状態の学生がたくさんいるとして、どこまで手を伸ばして支援をしていくべきなのかと考えてしまいます。
熊谷 支援や配慮の普遍化というテーマですね。つまり、そもそもこの社会というのは配慮の集合体と言って良くて、健常者とは配慮が必要ない存在ではなくて、存分に配慮を受けている人たちのことです。一方、まだ十分に配慮を受けてこなかった人たちもおり、平等に配慮を受ける権利があるということで、「合理的配慮」みたいな言葉が生まれるわけです。でも基本的には、配慮や支援は全員に必要というのが大前提です。
ただ、全員に必要ということはわかったけれど、じゃあどんな配慮が必要なのかはまた別の話です。つまり、配慮が必要かどうかという話と、どんな配慮が必要かという話は、レベルの異なる話なわけです。
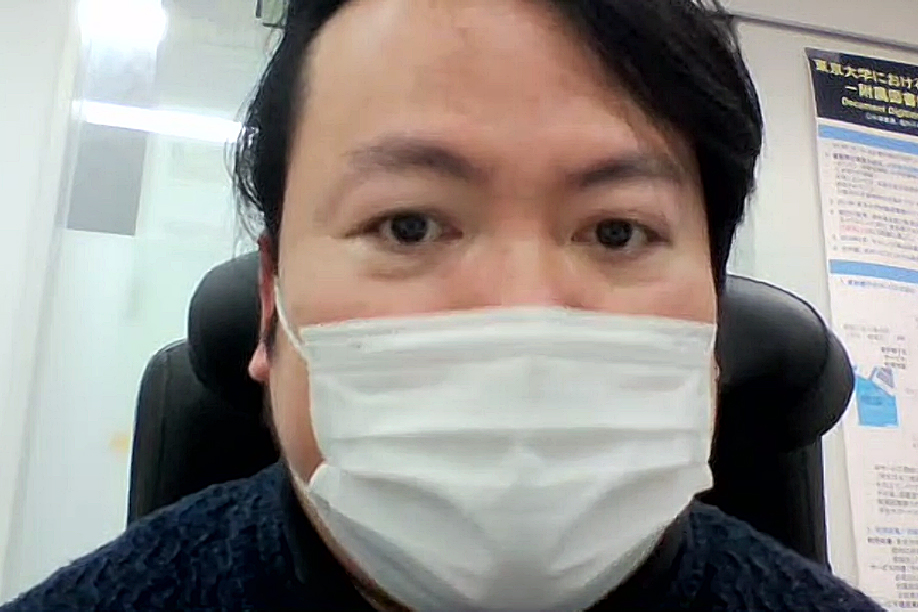
――どんな配慮がそれぞれに必要なのかを考えていけば、当然もっと詳しい情報が必要になります。
熊谷 そうですね。どんな配慮が必要かを具体的に考えるときには、まず体に関する情報が必要です。例えば「発達障害」と言うだけでは、体の情報としては不足していて記述が荒過ぎます。耳の聞こえ方はどうか、目の見え方はどうか、感情や思考のパターンはどうかなど、知りたいのはそのレベルです。配慮が必要なのは当然として、どんな配慮が必要かを具体的に考えていくときには、やはり体の特徴をつぶさに、細かに知る必要があります。
――障害のある人だけでなく、全ての人がそれぞれに配慮を必要としているということだと思うのですが、わざわざ障害者だけに「合理的配慮」という言葉が使われ、分けられているようにも思います。
熊谷 そこはどう考えるかで、もしも現場の運用の仕方として、支援する側が縦割りであるせいで、障害者と障害者以外の支援が分けられているという話であれば、それは本末転倒ですね。
大学も学生支援の文脈で、障害をもっている学生も他の学生と同じように支援をするというのが本来のあるべき姿でしょう。ただ現実にはなかなかそうはなっていませんよね。実際の制度設計が、普遍的な支援や配慮という理想的なコンセプトとややずれてしまっている状況があると思います。
ただ、具体的な支援をどう提供するかという面で言うと、捉え方は変わってきます。つまり、障害者であるかどうかに関わりなく、具体的な支援を提供するために、個々の体の特徴を細かく知っていくための専門的な部署が必要であるという話であれば、それは前向きなことだと思います。
ですから、具体的な支援を提供するためなのか、単に縦割りにこだわっているためなのか、いずれの理由で部署を分けようとしているのかということです。もしも後者であれば、それは制度的な瑕疵によって起きている議論だと言えるのではないでしょうか。
大学はどう対応できたのか
――今回、第1部ではほとんど書けなかったのですが、コロナ禍における大学の対応にかなり差があったのではないかと感じていました。どこも大変ではあったのですが、わりとうまくいった大学と、そうでないところがあったのではないかと。ただこれはごく一部の支援者や学生への取材で感じたことなので、裏付けられるものがないのですが、大学組織のあり方や障害のある学生に対してどこまで対応できたかといったことに、どうも差があったように思います。
熊谷 それは興味深いですね。一つの研究にもなりそうです。大学の組織って、ものすごく特殊な組織だと思います。一枚岩ではないですし、大学ごとに文化も違えば構造も違う。
また、部局が強い決定権をもっていて分権的な大学もあれば、中央が強い力をもっている大学もあると思うのですが、今回のような有事の際にはどちらが有利だったのか、どう作用したのかというのにすごく関心があります。
――取材でもう少し詳しく聞けると良かったのですが、今回はそこまで踏み込めませんでした。
熊谷 確かに、ややスケールの大きな話になるかもしれません。今、私がダイバーシティの文脈で非常に関心のある研究領域に、「高信頼性組織研究」注釈1という領域があります。これは原子力発電所とか、空港の管制塔とか、宇宙ステーションといった、ある閾値を超えた失敗が、大規模な事故につながりかねない現場組織に関するもので、そうした組織がどのように安全に運転を続け、コントロールできるかという研究です。
例えば原子力発電所には、非常に複雑で高度な構造が存在するのですが、同じ原子力発電所の中でも、事故が起きるところと起きないところを比較した研究が蓄積されています。
そこでわかってきたことは、事故が起きないところは、構造の複雑さに負けない文化の統制が効いているところだということなんですね。ここで言う「文化」には三つの要素が含まれています。
一つは、その組織がなんのために存在する組織なのかというビジョンとミッションを、メンバーの隅々までが共有しているかどうかです。要するに、組織の存在意義や価値を個々のメンバーが深く熟知しているかということ。二つ目は、メンバー同士が普段からお互いのもっている情報やスキル、趣味、個人的経験などを共有し合えているかどうか。最後の三つ目は、先入観や偏見を疑えるかどうか。誰しも無意識に思い込んでいることや想定していることがあるのですが、それを自ら疑ってかかれるかどうかです。たとえ想定外のことが起きたとしても、その想定外の出来事を無視せず正確にキャッチして、思い込みがあるかもしれない自らの想定の方をアップデートできるかどうか。
これら三つの文化が備わっていれば、高度に複雑な構造をもった組織でも、大きな事故が起き難いということが言われてきました。私はそれが大学にも重要なヒントを与えてくれているように思います。
文化は「人」に関わること
――今回のことで言うと、大学の執行部が障害のある学生のことは支援室に専門知があると考えて、かなり早い段階で、障害のある学生に対してどうすればいいかと支援室に尋ねられたところもありました。こういった有事の際、障害のある学生にはどういうことが起こり得るのか、なにに気をつけなければいけないのかと。そこで伝えたことが今度はトップダウンで全学に行き渡り、例えば課題が多すぎるのは大変だから少なめにしようとか、できるだけプラットフォームを統一しようとか、そうしたことが周知できて、障害のある学生だけでなく、障害のない学生に対しても有効だったのではないかということでした。そうした大学ではやはり、その後の対応も非常にスムーズに進んでいった印象があって、素晴らしいなと思い聞いていました。
熊谷 おもしろいですね。まさに二つ目の、メンバー同士がお互いのもつ専門知や情報を共有し合えているからこそなし得たことではないでしょうか。
――ただ、それがなぜできていたのかと聞くと、障害に理解のある理事が一人いたからとか、支援室長が執行部に意見を言える人だったとか、わりとそこは人に依存しているのかなと感じました。でも結局「人」なのかもしれないですけど……。
熊谷 そうですね、構造というのはモノですが、文化は人だと思いますね。どうしても大きな組織になるとお互いの顔がみえなくなるので、基本的に人間不信のマネジメントに偏りがちです。そうなると、人よりも、ルールや明文化された仕組みに頼りたいというインセンティブが肥大化して、それがリスクを高めてしまう側面があります。
だからある意味では、キーパーソンがいたことはなにも悪い話ではなくて、文化が機能していた証だと思います。ですから、そうしたヒューマンファクターを取り除くのではなく、どう増やしていくか、どう維持するかを考えていく必要があるのかもしれません。
なんとなくこれまで、構造がしっかりしてないとダメな組織みたいなことが論じられ過ぎていたと思うのですが、特に有事の際は、構造だけでは十分ではないということが重要なポイントだと思います。
――もう一つ、ビジョンやミッションの共有に関わる話で、一度目の緊急事態宣言が解けて大学が動き出すとなったときに、学内で教員や職員に向けて、急いで障害学生支援の研修をされた支援室がありました。障害学生になにが起きているのかを言わなければいけないと思ったそうで、そのときはみんなに余裕がなくなっていたので、障害学生たちへの配慮や支援の必要性がかき消されてしまうんじゃないかと怖かったと言います。
熊谷 すごく共感します。構造と文化の対比を行った研究の中で、構造が提供するのは手段で、文化が提供するのは目的であると整理されています。目的を見失った組織は事故を起こすという非常にシンプルな整理なのですが、そもそもなにをしなければならないのか、これまで培ってきたものをかなり初期の段階で再確認したというプロセスは、非常に納得のいくことです。
目的をもう一度復習することで、眠っていた知恵が自ずと立ち上がる。大きな組織では、上位下達ではなく、目的を参照しながらメンバー各々が自主的に判断してしまった方が良い場面がけっこうあるんですよね。ですから現場の知恵をいかすためにも、文化のリマインドは非常に重要な作業だったと思います。
全員が当事者に立ち戻る
――最後に、私たちがこれからなにを考え、行動していくべきなのか、ぜひ今考えておられることをお聞かせください。
熊谷 コロナ禍で気付いたことや変わったことのうち、良いことを今後も選択肢として残したり、仕組みを変えていくとなったときに、やはりそこに抵抗する人たちや組織もあるだろうと思っています。
変化が起きるときというのは、必ずその変化に抗おうとする人たちがいる。でもその相手も困っている当事者だったり、切実なニーズがある人たちであったりするんですね。
例えば障害者のコミュニティも、今まで獲得してきたことを当然ながら死守しようとします。それはみる人からみたら保守的にもみえるのですが、その背景には切実なニーズがあるわけです。
ですから、お互いが困りごとを出し合えるような、相手がなにを心配しているのか、なにを抱え込んでいるのかということを、障害/健常の枠を超えて出し合えるような文化をつくることが、今後ますます大切になっていくだろうと思います。
健常な人も含めて、誰もが自分も困っているということを認め、向き合っていくためにも、選択肢の一つとして、当事者研究があるのではないかと思っています。特に、大学や企業の役員、執行部にもやっていってほしいと願っています。みんなが当事者に立ち戻って、オープンにしていくことからなにか動き出していくのではないかというのが、私の今考えていることです。
2021年2月8日Zoomにて収録
注釈一覧
注釈1
高信頼性組織研究
スリーマイル島原子力発電所の事故(1979年)、チェルノブイリ原子力発電所事故(1986年)など、数々の巨大事故の発生を背景に、1980年代後半にアメリカで誕生した研究。高信頼性組織を実現している組織は、変化に気付ける「鋭敏さ」、その気付きを上司に伝えられる「正直さ」、上司がその報告を受け止め確実に対応する「慎重さ」、権限に関係なく能力のある人が対応する「柔軟さ」を兼ね備えているとされる。また有事の際には分権的な組織に移行する必要があると考えられる。
熊谷晋一郎・くまがやしんいちろう
1977年、山口県生まれ。新生児仮死の後遺症で脳性麻痺になり、以後車いす生活となる。東京大学医学部医学科卒業。東京大学先端科学技術センター准教授、小児科医。専門は小児科学、当事者研究。主な著書に、『リハビリの夜』(医学書院)、『当事者研究―等身大の〈わたし〉の発見と回復』(岩波書店)、綾屋紗月氏との共著に『発達障害当事者研究―ゆっくりていねいにつながりたい』(医学書院)、『つながりの作法―同じでもなく 違うでもなく」(NHK出版)、國分功一郎氏との共著に『〈責任〉の生成―中動態と当事者研究』(新曜社)など、多数。