本当のニーズを探り当てる
――選択の幅を広げることはとても大事だと思います。でもある選択肢を求める人の数が少なかったり、周りに理解され難いものだと、なかなかそれを求めていくことが難しい場合もあります。
斎藤 先ほども言いましたが、不登校児の中には、休校がずっと続いてほしいと願う子もいました。けれどもこれは簡単には口に出せない。多くの子どもたちが再登校したがっているという前提がある世界では、「登校しない方が楽で良かった」とはなかなか言い出せないですよね。そういう意味で、マイノリティの人がこれまで以上に声を上げ難い状況があった可能性があります。
そのことと共通しているように感じたのが、今回のコロナ禍で、なぜか感染した人が世間に向けて謝罪していたことです。これはなかなか異様な行為で、他国ではほとんど例を見ない奇妙な光景でした。おそらくみんな、人に迷惑をかけることに非常に敏感で、そのために生じた現象だと思います。そうした社会では、病んでしまったり障害をもつことも、人に迷惑をかけてしまうことと考えられ、避けるべきと思われる傾向があります。周りの人のことを考えると、なかなか自分の本音や弱音を言い出せなくなります。
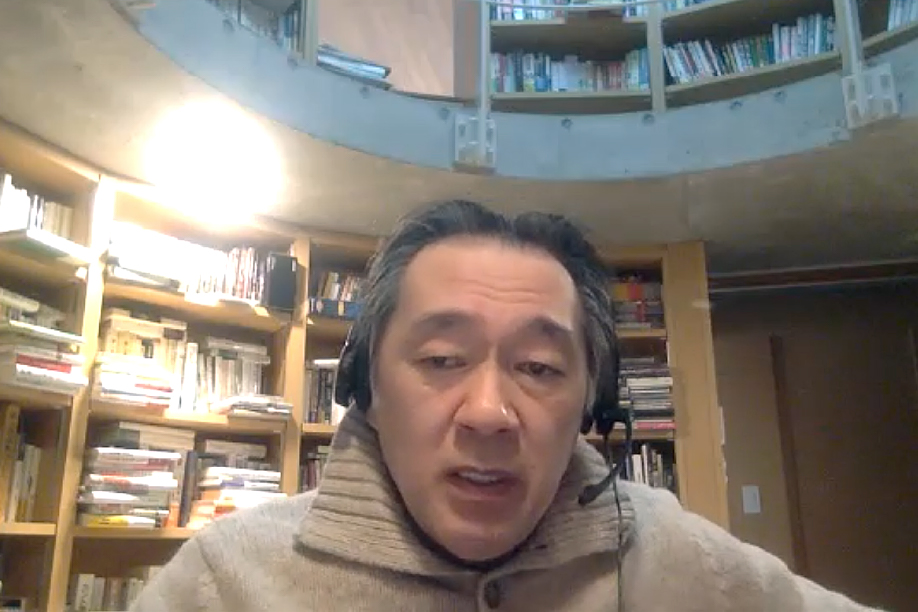
――本当のことを言ってもいいんだと思えるためには、周りがそのことに気付いたり、それを言ってもいいと思える環境を作らなければなりませんよね。大学でも、学生たちのニーズをどう引き出し、対応するかが課題としてあります。
差別解消法の合理的配慮の提供では、学生本人のニーズを大学に伝える仕組みとして、学生と大学との「対話」が前提とされています。そこでは、自分のことは自分が一番わかっているはずだから、学生自身がそれを伝えていくことが想定されているのですが、例えば発達障害傾向のある人や知的障害のある人の場合、なかなか自分のニーズみたいなものをはっきり相手に伝えることは難しいですよね。
斎藤先生はオープンダイアローグをはじめ、これまで様々なところで対話について言及されてきました。このことをどうお考えになりますか。
斎藤 哲学者の國分功一郎さんが、「欲望形成支援」という言葉を使われていました注釈1。これは非常に重要な言葉で、ひきこもりにしても発達障害にしても、それまで受けてきたさまざまな抑圧のせいで、自分のニーズがわからない状態になっていることがあります。つまり、公式的なニーズは埋め込まれているけれども、それがその人の本当のニーズかどうかわからないという状況です。だから支援者に何をしてほしいかと聞かれれば、「○○してほしい」と言うことはできるけれども、それが欲望から出てきたニーズなのか、社会適応のために出てきた建前的ニーズなのかが本当のところでよくわからないということです。
私が考えている対話とは、決定や合意のためにするものではありません。対話の目的は、対話をする者どうしが、それぞれの考えやそれぞれの主観のありようの違いを掘り下げることだと言えます。あくまでも事実や真実を追求するのではなく、それぞれの主観世界のありようを交換し合うということです。大事なことは、支援者は客観世界に生きていて、当事者は主観世界に生きていると分けて考えるのではなく、支援者も主観世界をもっていると考えることです。その上で、お互いの主観世界を交換し合う。その中でだんだんと、欲望の端っこが見えてくると考えるんですね。
――支援者はどうしても、マニュアルや診断書といったものを基に客観世界をつくり上げてしまいがちですが、それだけでは当事者の本当の姿は見えてこないと。
斎藤 オープンダイアローグをしていると、毎回本人のニーズが変わっていくことを経験します。これが本来の姿だと思っていて、精神科の場合、患者さんのその時々のニーズを探り当てそれに柔軟に合わせていくことが治療の5割以上を占めるといっても過言ではありません。身体科のように、治してほしいというニーズが明確に最初から最後まであるわけではないのです。
おそらく発達障害の人もそうだと思うのですが、治したいとか変わりたいという気持ちと、治されたくない、変わりたくないという気持ちが半々ぐらいあって、そのへんのアンビバレンスをうまく処理できないから、表面的には「治してほしいです」としか言いようがない状況があるんだと思います。だけど本当は治してほしくないという部分も汲んでいかないと、本当のニーズには辿り着けない。矛盾するようなことが出てくるまで対応を続けていかないと、それこそ非常に表面的な合意形成しかできないのではないかと考えています。
ですので、いわゆるインフォームドコンセントをモデルとするような、最初の段階で一度合意形成したら、その後もずっと同じ契約内容でいくということはほぼあり得ません。ニーズは毎回変わることが前提になります。そう考えると、対話も、その都度契約をし直すような関係と言い換えられるのではないでしょうか。
支援の形式と本質
――本当のニーズや欲望を探し出すとなると、毎回変わっていく内容に付き合っていくしかありませんが、なかなか難しい部分もあって、合理的配慮の内容が毎回変わっていけば、教員も対応できないし支援者の手も足りないということが起きてくると思います。一定の手続きや枠組み、大学組織という状況、条件の中で、どう支援や配慮を提供していくかという話にならざるを得ません。
斎藤 それはやむを得ないことで、制度的に支援をやっていく上では仕方のないことです。けれども支援者が、とりあえず形式に合わせながらも中身をある程度変えていくことはできると思います。
つまり形式的な評価を取り込んで、PDCAに則ってしっかりやってますよと外見上は取り繕いつつ、中身は対話的にやるというのが十分にできると思っています。この両者は矛盾しません。そうした方法をゲリラ戦を展開するようにやっていけば、だんだんと支援現場も変わっていくのではないかと期待しています。
――個々の場で、学生が本当は何がしたいのか、どう生きていきたいのかというところまで探っていくような支援を展開するということですか?
斎藤 まさにそういうことですね。学校に適応できるような支援も大事ですが、内実的にはもう少し、本質的なところに届くような対応を続けていく。私の楽観的な予測では、そうした支援の方がおそらく成果が上がっていくでしょう。あとは結果オーライで、「成果が上がっているからいいでしょ」と言えるのではないかと思います。
「困り方の雛形」を支援者が与えてしまうとまずいんです。私が専門とするひきこもり支援では、ひきこもっている人の最初のニーズって「放っといてくれ、俺にかまうな」ですからね。そういうことをまずは言ってもらってもいいんです。そこから親御さんを通じて関係修復しながら関わっていくと、今度はニーズが変わってきて、実はしんどいんだ、きついんだということが出てくるようになるんです。いかに型にはめないかということですね。
今を記録し、未来につなげる意味
――コロナ禍で大学にも様々な変化が生じて、それによっていろいろな気付きがあったわけです。ですが、これらのことは忘却される恐れがあって、そうならないようにしなくてはいけないと書かれていました注釈2。なぜ私たちがこのコロナの経験を忘れ去ってしまうのか、文章を読んで非常に納得しました。
斎藤 このままではコロナ禍の経験は忘却されていくだろうと書いたのですが、そのきっかけは、20世紀初頭に流行したスペイン風邪に関する本を読んだことでした。スペイン風邪も、多い推定で1億人が亡くなった人類史上最大級の厄災だったのですが、驚くべきことに、ほとんど年表にも残っていないし、同時代を生きた有名な小説家にも全く取り上げられなかったんですね。でも実際、私もこのコロナによるパンデミックを経験すると、確かにこれは忘れてしまうのではないかと感じました。
なぜかと言うと、「ピーク・エンドの法則」というものがあって、体験の記憶というのは、一番しんどいときと一番最後の経験が残るものなのですが、コロナ禍において一番しんどかった時期の記憶もあまりないし、終わるときはおそらくフェードアウトする感じになり、クライマックスの非常に乏しい経験になってしまうだろうと。
それから、精神科医の宮地尚子さんが「トラウマの語り」が持つ構造注釈3をドーナツ型の島である「環状島」をモデルに説明していて、ここからも着想を得ました。
この環状島には外海と内海があって、内海の中心をゼロ地点、つまりトラウマの核心部分とします。トラウマを経験した人はその経験が重いほど、この内海で沈黙します。この内海の周りには、内海に通じる内斜面と外海に通じる外斜面が稜線を挟んで続いており、トラウマを経験する本人以外の人たちというのは、基本的にこの外斜面にいて、内海で当事者が沈黙しているのと対照的に、稜線から外側にいけばいくほど声をあげることができるとされています。
東日本大震災は2021年3月で10年を迎えますが、この震災に関しては、アートや映画、小説などの形で、膨大な語りや表現活動が行われてきました。これらはそれこそ、外斜面より外側にいる非当事者がやってきたことで、あらゆるところで語り継がれ、人々の記憶に残り続けています。
しかし今回のコロナは、誰もが自分は感染しているかもしれないと思ったという意味で、全員が当事者である可能性がありました。また少なくとも、誰もが強く認識した物理的なグラウンド・ゼロもありませんでした。つまり社会的トラウマが形成される上で重要な条件と私が考えている「環状島」が形成されないのです。こうしたことから、犠牲者が多いにもかかわらず社会的なトラウマになり難く、それゆえ忘れ去られてしまう可能性があると考えたわけです。
――忘れられることの一番の問題はなんなのでしょうか。
斎藤 それは、今後同じようなことが起こったときに、その初動を遅らせてしまうことです。こうしたパンデミックは、今後これまでにない頻度で起こり続けると指摘する専門家もいますが、その度に同じことを繰り返す恐れがあります。
例えば、今でもずっと感染症対策のために、緊急事態を強化していくべきか、それとも経済が回らなくなると自殺者が増えるなど犠牲者が出てしまうので、大げさにとらえるべきではないのではないかというジレンマがあって膠着状態です。あるいは女性の自殺者が増えていることや、障害をもった人や貧困層にしわ寄せがいっているのではないかという指摘もあるのですが、現状分析も問題の特定も何もかもが追いついていません。
ですので、今後同じようなパンデミックが起こったとき、繰り返し一から考えなくてもいいように、今起きていることの検証とそれへの対策をしっかり考える必要があります。
私が提唱するのは、今起きていることを忘れないために「終息記念日」のような日を設け犠牲者を追悼する祭祀化をすること、そして記録をして、語り続けることです。ですので、今回のような形で記録を残することは、今後同じことを繰り返さないためにも、非常に重要なことではないかと思います。
注釈1
欲望形成支援
國分功一郎さん(哲学者・東京大学准教授)が、「意思決定支援」に代わる言葉として提案している。「意志(意思)ではなく欲望。決定ではなく形成です。人は自分がどうしたいのかなどハッキリとはわかりません。人は自分が何を欲望しているのか自分ではわからないし、矛盾した願いを抱えていることも珍しくない。だから、欲望を医師や支援者と共同で形成していくことが重要ではないか」國分功⼀郎・熊⾕晋⼀郎『〈責任〉の⽣成―中動態と当事者研究』(信曜社、2020)p.200
注釈3
トラウマの語りが持つ構造「環状島」モデル
宮地尚子さん(精神科医・文化精神医学・一橋大学大学院社会学研究科教授)が、言葉にならないはずのトラウマが、伝達可能な言語となっていかに公的空間に現れ、扱われているのかを説明したモデル。被害当事者、支援者、遺族、傍観者などがそれぞれどのような位置、関係にあるのかを、立体的なドーナツ型の島をモデルに説明している。
斎藤環・さいとうたまき
1961年、岩手県生まれ。1990年、筑波大学医学専門学群環境生態学卒業。博士(医学)。爽風会佐々木病院精神科診療部長を経て、2013年より筑波大学医学医療系社会精神保健学教授。専門は思春期・青年期の精神病理、精神療法、および病跡学。著書に、『オープンダイアローグとは何か』(医学書院)、『ひきこもり文化論』(紀伊國屋書店)など多数。『関係の化学としての文学』(新潮社)で2010年度日本病跡学会賞受賞。『世界が土曜の夜の夢なら ヤンキーと精神分析』(角川書店)で2013年第11回角川財団学芸賞受賞。『心を病んだらいけないの?うつ病社会の処方箋』(新潮選書)で2020年第19回小林秀雄賞を受賞。