人は人と出会うべきなのか
――斎藤先生が2020年5月30日に「note」に書かれた「人は人と出会うべきなのか」注釈1で、人と人が出会う場には必ず暴力が潜んでいて、それを「臨場性の暴力」と表現され、このコロナ禍では人と会わなくなったことでそうした暴力にさらされる機会がずいぶん減り、楽になった人がいるのではないかと書かれていました。
ここで言う暴力とは、もちろん物理的な暴力を指すのではなく、それこそ「赤子ですら薄い闘気がある」と書かれているように、誰しもが他者に対して侵襲的であらざるを得ないことから生じるもので、特に人と人とが出会う場面では必ず存在するものだと述べられています。
そう考えると、まさに人と人とが接し合う医療や支援の現場には常に関係してくるテーマで、実際に支援者やカウンセラーを中心に反響が大きかったと聞きました。
斎藤 今までネット上で発表した私の文章の中で一番反響があったのではないでしょうか。それも易しく書こうなんて全然思わず書いたので、非常に驚きました。おっしゃるように、カウンセラーや支援に関わる人たちの反響もすごく大きかったですね。
まずこれは、私自身の当事者研究と思って書いたところがあります。この文章を書いた2020年5月というのは、ちょうど日本中がひきこもって対面の機会が減った時期です。このとき、私自身が非常に楽だったんですね。人と会わないで済むのが気楽でいいなと。
誰かと会う約束って、会う直前まですごい憂鬱なんです。それは人が嫌いとかではなくて、好きなんだけれども会いたくない。これは、暴力性というものに自分が敏感であるせいだろうと思っていたのですが、人と会う機会が減ってそれを楽に感じている自分がいて、やはり人と会うことには暴力性が伴っていたのだと改めて思ったわけです。
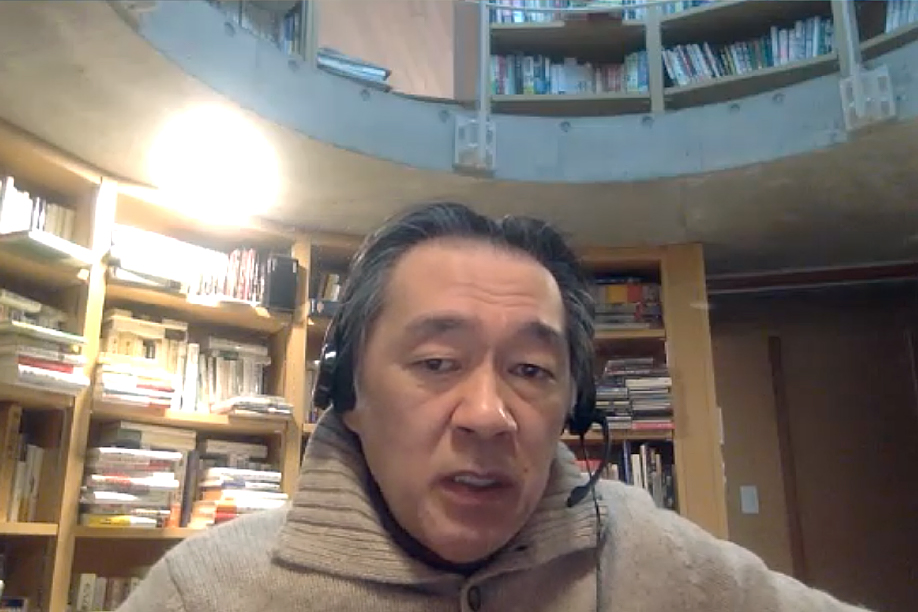
――確かに人と触れ合いたくないわけではないけれども、会うのはそれなりの力がいるし、ときに億劫になることもありますね。その感じ方は人によって違うと思うので、それがかなり強い人にとってこのコロナ禍は、心の安寧が保ちやすい時間になっていたのかもしれません。
斎藤 学生にも、対人恐怖や対人緊張が強くて学校に来れない人がたくさんいました。そういった人たちにとって、リモート授業は救済になっていたと思います。リモート授業の期間中にしっかり勉強ができて、その助走期間があったおかげで、これまで参加が難しかった通常の対面授業にも参加できるようになったという話も聞きました。
ただ大事なのは、人と会うことをなくしてしまえばいいといった単純な話ではないということです。人と会うことはしんどいことだけれども、引き受けていかなければならないことでもあります。なぜなら、人と会わなければ社会は回らないし、自分も社会の中で生きていけなくなるからです。
暴力なくして社会は生まれず、成り立ってもいかないわけで、臨場性にはそうした相反する両面が含まれています。それをどう考え、今後につなげていくか。それがこのコロナ禍で問われ始めていると感じています。
――それを考えていくためには、暴力性というものにかなり自覚的である必要があります。
斎藤 私自身も精神科医として、自身がもつ暴力性に配慮しながら面接することが求められています。これは対人援助の人たちには共通する話で、支援ですら暴力になってしまうということに、私たちは十分気をつけなければなりません。
ひきこもり支援でも、いわゆる「引き出し業者」という人たちがいます。この人たちは当事者の家に上がり込んで力ずくで寮に連れて行き、強制的に就労訓練をしたりするんですが、明らかに犯罪行為なのに、世間は必ずしもそうは捉えていません。非常にすばらしい活動だと言う人もいるし、やっている人たちも善意でやっていると言うのです。
これは支援が暴力化した最悪のパターンですが、実際に善意と人助けの気持ちがあれば、こうしたことが許されてしまう場合があります。ですので、支援をする人たちは特に、暴力性というものに自覚的でなければならないと思います。
――臨場性がはらむ暴力に自覚的になるというのは、例えばこれからの支援を考えたとき、場合によっては、支援者と被支援者が直接会うのではなく、会わないことも含めて支援のあり方を考えていかなければならないということでしょうか。
斎藤 そうですね。例えば私がずっとやり続けている「オープンダイアローグ」注釈2も、今まで対面でやってきたのを一時中止にして、Zoomで再開することにしました。
もともとこの手法は、そこにいる人たちが身体的な反応によって共感を表明するとか、身体が居合わせていることに意味を見出すような実践でした。ところが実際にZoomでやってみると、意外なほどにクライアントさんの反応がいい。中には、「対面とあまり変わりません」とか、「家から参加できるから楽です」などと言う人もいて、リモートでやるメリットを非常に感じています。遠隔地から気楽に参加できるのも良くて、例えば水戸在住の人と横浜在住の人が一緒に治療チームを組んで、東京在住のクライアントの相談に乗るなんてことができるわけです。
もちろん対面のリアリティをなくすわけにはいかないのですが、むしろ対面の方を臨時的な保険として、通常時はZoomでやることすらあり得るんじゃないかと考えています。
――今回の取材で複数の支援者から、学生と会えなくなったことのデメリットをたくさん聞きました。でも一方で、学生との面談に初めてZoomを使った支援者もいて、その中で、今までにないほど学生が話すようになったと驚いている人がいました。その学生からは、「画面越しだと目が合わないから話しやすい」と言われたそうで、今まで意識してなかったけれど、自分の視線が圧力になっていたのかと思ったそうです。
でもやはり、やりづらさを感じていた支援者も多くて、会わなくなったことで、これまで言葉以外から感じ取れていた学生の様子がわからなくなったとか、斎藤先生が言われた身体的な感覚が失われたことが大きかったのだと思います。
斎藤 それはよくわかります。ただ支援に限らない話ですが、ある種の「身体神話」みたいなものが日本には強くあって、身体性が付随していなければ価値がないみたいな物語が信じられ過ぎているきらいがあります。
私自身もリモートには身体性がないからダメだという先入観があったので反省しているのですが、意外と体験してみるとできることもある。そうしたことの検証がこのコロナ禍で進めばいいなと思います。
多様性に配慮した選択肢を残していく
――オープンダイアローグの話がありましたが、大学でも、発達障害のある学生らが当事者で話し合うグループ活動やピア・サポート支援をやっているところがあります。こうした活動がコロナ禍でできなくなったために、学生らが孤立しないようZoomで続けていたところもありました。
そこにこれまで対面形式では参加したことのなかった学生が初めて、リモートになって出てくるようになったと聞きました。ただ活動中の90分間、ビデオをオフにして発言もせず、名前を表示させるだけだったそうです。でもおそらく本人からすれば、なにか意図や意味があって参加していたんだと思います。
その支援者が言っていたのですが、これまで対面でやっていたときにはまずその場に出て来ることを求めていたので、この学生の場合にはそれへの適応が難しくて、参加できていなかったのかもしれないと。もしこれまでも顔を見せることなく、その場に身を委ねるだけという参加方法があったのなら、その学生は参加していたかもしれない。
そう考えると、誰でも参加できますよという場やコミュニティであっても、実は見えないハードルが存在していて、それを乗り越えられる人しか参加できなかったのではないかということでした。学生の方がこちら側の環境に合わせなければならないみたいな構図があったのかもしれず、それもある種の暴力として働いていたかもしれません。
斎藤 今の話は非常に印象的です。当事者研究をされている綾屋紗月さんが、人の中で話すのは苦手だけれども、人が楽しそうに話しているのを眺めていたい気持ちはあると書かれています注釈3
またこれは別の人が言っていたことですが、Zoomというのは、どこかで誰かが自分の陰口を言っているのではないかといった、妄想的な発想になり難いと言っていました。
それを聞いて、なるほどなと思いました。Zoomというのは、同じサイズの顔が並んでいるだけのフラットな空間ですから、奥行きや深みがありません。それが居心地の良さにつながっている可能性があります。
身体神話というのは、逆にそうした奥行きや深さに価値を置いていたところがって、ある種の感受性をもった人には辛かったかもしれない。今そうしたことを見直す非常に良い機会じゃないでしょうか。
――心配なのは、コロナが収束すれば、いっきに「三密を復活させよう」みたいな方向に流れていくかもしれないことです。
斎藤 それはちょっとマズいのではないかと私は思います。コロナ禍のひきこもり生活で、私のように楽になった人はかなりいたはずです。臨場性に対する耐性や忍容性は人によって様々で、これは障害の有無に関係なく、感受性というものが人それぞれ多様であるという話です。
今後こうした多様性への配慮が求められてくるだろうと思うのですが、今の学校現場には、そうした配慮がほとんどありません。一斉休校の期間中に言われていたことは、「子どもたちはみな登校したがっている」ということでした。これは非常に雑な前提で、本当は不登校になって楽になったり、それで勉強ができるようになったとか、救われた子どももいっぱいいました。それを踏まえれば、今後はもう少しハイブリッドな方法を取り入れ、選択肢を増やしていくことを考えていただきたいと思います。
――実は障害のある学生の中には、コロナになる前からリモートで授業を受けたいというニーズがかなりありました。でも技術的な理由や学びの本質が損なわれるといった理由で、それが認められてきませんでした。ところが今回のように社会全体が変わると、今まで許されてこなかったリモート学習がいとも簡単に認められ、むしろその一択になった。この変化は、障害ってなんなのかということを改めて考えさせるものでもあったのですが、いずれにしても、今後もリモート学習を希望する学生は一定残ると思います。それも選択肢の一つとして残していくべきということでしょうか。
斎藤 当然そう思います。それこそ障害のために移動が困難な学生にとっては、すごく役に立つインフラではないでしょうか。改めて対面のもつ価値や意味がきちんと検証されるべきで、対面の自明性というものを根底から疑った方がいいと思います。「なんで会わなきゃいけないの?」ということが当然出てくるわけです。単に会うことを否定するのではなく、会うことにメリットがある場面と、メリットがないどころか会うことが非効率な場面と両方あるわけですから、その評価をこの際しっかりやりましょうということです。
大学の授業でも、医学の実習など臨場性がなければ意味がないものもあれば、座学の授業の中にはリモートの方が良いものもあると思います。
対面でやることに本当に意味があるのか、あるのなら対面でやるしかありませんが、それほど意味がないものもあるはずなので、選択の余地を大幅に残しておいた方がいいんじゃないかと思います。
後編につづく
注釈2
オープンダイアローグ
1980年代にフィンランドで生まれた統合失調症患者に対する対話を中心とした治療法。医療者と患者とはフラットな関係が目指され、入院や薬物治療もできる限り行われない。斎藤環さんはオープンダイアローグ・ネットワーク・ジャパンの共同代表を務める。
注釈3
綾屋紗月『発達障害当事者研究―ゆっくりていねいにつながりたい(シリーズ ケアをひらく)』
自身も発達障害の当事者として、当事者研究を行う綾屋紗月さんと、#8、#9で登場する熊谷晋一郎さんとの共著。医学書院から2008年9月に出版されている。
斎藤環・さいとうたまき
1961年、岩手県生まれ。1990年、筑波大学医学専門学群環境生態学卒業。博士(医学)。爽風会佐々木病院精神科診療部長を経て、2013年より筑波大学医学医療系社会精神保健学教授。専門は思春期・青年期の精神病理、精神療法、および病跡学。著書に、『オープンダイアローグとは何か』(医学書院)、『ひきこもり文化論』(紀伊國屋書店)など多数。『関係の化学としての文学』(新潮社)で2010年度日本病跡学会賞受賞。『世界が土曜の夜の夢なら ヤンキーと精神分析』(角川書店)で2013年第11回角川財団学芸賞受賞。『心を病んだらいけないの?うつ病社会の処方箋』(新潮選書)で2020年第19回小林秀雄賞を受賞。