コロナ禍の合理的配慮
村田 さっき言われた話の中にもあったのですが、特に精神や発達障害の領域で、私たちも合理的配慮のあり方がわかりにくくなっているように感じました。
例えばADHDがあって、スケジュールの管理がうまくできなかったのでレポートの締切を延長するとか、あるいは対人恐怖があってみんなの前で発表することが難しいので個別の発表に変更するとか、こういったことをこれまでは合理的配慮として提供していたわけです。でもそれがコロナの状況になって、レポートの締切を延長することや発表方法の代替、画面に映りたくないのでビデオをオフにしたいとか、そういうことが障害だけを理由とせず、様々に出てきました。それも本人たちの努力ではどうにもならない点は、障害のある学生と変わらない。そうなると大学側もなんらかの配慮をするしかなくなる。
今まで合理的配慮として一定の条件設定の中でやってきたことが、特に合理的配慮としてやる必要がなくなったとも言えます。もしかすると今後、合理的配慮の捉え方も変わっていくかもしれない。
合理的配慮というのは、配慮という言葉が使われるがゆえに、単なる「気づかい」とか「心配り」と思われがちなところがあります。でもやってきたことは、アクセスの保障や権利の保障だったわけです。そのために必要なことは、リソースの提供でした。つまり、学生が困っているから助けてあげるというより、できるようになるための方法や手段を提示したり提供するだけ。これは気をつかって助けてあげることとは異なります。
でもこの非常事態の中で教員が学生に行っていることは、厳密には権利保障というよりも、気づかいの中での配慮なんですね。だから、我々がこれまでリソースの提供だと思ってやっていたことが、大変だから助けてあげようという配慮に内包されていっているような印象を受けます。もちろんこれが差別解消法の「事前的改善措置」の一環になるのだとすれば、それは一つの方向性だと思います。でもそうでないとすれば、合理的配慮とは何かということにもう一度目を向けていく必要があると思います。
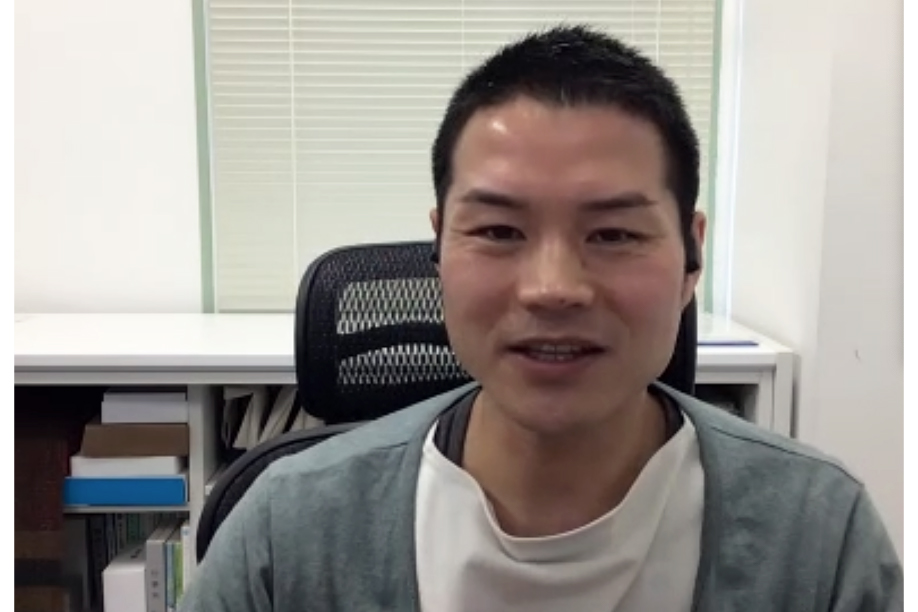
荒井 合理的配慮という概念が、まだまだ社会の中できちんと合意形成されていないようにも感じます。
障害者運動にずっと関わっていたDPI日本会議の尾上浩二さん注釈1とお話をしたとき、「障害者の方が生きやすい社会を求めたことは一度もない」とおっしゃっていて、それは確かにそうだな、と思いました。
でも合理的配慮って下手をすると、出席日数の足りない学生が診断書を出したら大目に見られるといった形で使われることもありますよね。これは合理的配慮の理念からすると違う気がします。
今、学生が様々な困難な状況にある中で、非常に意地悪な表現をすると、現場の教員は「みんな困っちゃったから大目にみる範囲を広げましょう」となっている。その中でいろいろな学生がいろいろな理由で救われたり、なんとなくやり過ごせている状況があるかもしれない。例えばどうしても課題のスケジュール管理ができない学生とか、対人恐怖でプレゼンテーションができない学生も、この混乱の中でなんとなく「困りごと袋」みたいなところに他の困りごとと一緒に入れられている状態。
でも、コロナが落ち着いて日常に戻り、「困りごと袋」の中に入っていたものをもう一度整理しましょうとなったときに、あなたは本当に困ってるの? あなたは本当に支援が必要なの? と審査されるような状況がやってくるんじゃないか。いつまでも大目にみるわけにはいかないという思いが強まり、「支援は『本当に必要とする人』にするべき」といった目線が、コロナの前より厳しいことになってしまうんじゃないかと危惧しています。こういう場合の「本当に~」が危ういことを、私たちは知っているわけです。

村田 改めて、合理的配慮と他のサポートや配慮との違いを意識しながら、私たちも動かないといけないと思います。私もよく研修で、合理的配慮を英語に訳してみてくださいと言うんですが、多くの人が “support” “service”って訳すんですね。正解の“accommodation” とする人はほとんどいない。だからやっぱり、配慮という言葉が本来の意味から離れて使われているように感じます。
荒井 やはり合理的配慮の理念をどう守っていくかが大事だと思います。でも実際には、合理的配慮って「できる範囲で優しくしてあげること」って……
村田 みんな思いますよね(笑)だから結局、気づかいの配慮になっているんですね。困っているから、あるいは弱い立場だからなんとかしてあげなきゃいけないっていう。でも実際に求められているのは、方法の調整だったり手段の変更なんです。
コロナ禍で、他の困りごとと一見同じことを言っていると思われると、荒井さんのおっしゃる支援のトリアージに巻き込まれてしまうと思います。
回復過程を見据えて
村田 今後のことはまだ全然わからないのですが、後期セメスターに入ってからの支援現場は、ただただ混乱していた前期に比べれば、少しずつ慣れも出てきて、ある意味では回復の過程を歩み始めているように感じます。そして実はこの回復の過程の中で、新たなディスアビリティが生じていくのではと危惧しています。
やや俯瞰した言い方になるのですが、今のようにあらゆる人が同時に困るような状況って、過去にさかのぼってもほとんどなかったですよね。極端なことを言えば、第二次世界大戦以来ということにすらなり得る。その先にイメージするのが、みんなが一斉に同じ方向を向いて生きていたような、戦後の経済成長期の姿です。こうしたときには、多くの人が同じ価値観なり考え方を共有するので、マジョリティが中心になりやすくなる。でも、たまたまなんらかの事情でその価値観を共有できない人がいると、その人はどんどん周縁化していきます。障害の歴史をたどっても、教育や労働が効率化の名の下に画一化されていく中で、そこに乗り切れない人たちが障害者として生み出され、後回しにされてきたわけです。
コロナ禍で広がったリモートワークやオンライン授業によって便利になった側面もあって、一定の評価を得て今後も広がっていくだろうと思います。ただ一方で、その方法に馴染めないことが新しいディスアビリティになるかもしれない。支援に携わる者としては、そこを見逃さないようにしなくてはいけないと思います。
ただ一縷の望みがあるとすれば、今の話とは表裏一体で、これまで「多様性」と言われる理念として語られてきたものがあります。コロナ禍では、なにが正しいかが揺らいだ。本当に会うべきなのか、オンラインで済むのではないかとか、私たちは立ち止まって考えたわけです。出勤せずリモートで仕事ができるようになったことも、多様性の幅をみんなが経験したことになるだろうと思います。
大学も、教室に行かないと授業が受けられず、教育が成立しないと思われていたけれど、そうではなくなった。こうした大きな変化を経験した先に、新たな価値観が生まれるのではないかという希望と、ますます一部が置いていかれ、切り捨てられるのではないかという恐れの両方が、私の中でうごめいています。
荒井 アフター・コロナの話をするのは早いかもしれないのですが、確かにまたリアルな対人関係の世界に戻ったときに、つまずきを起こす学生が出てくることにも気を付けなければなりません。特に対面に対応できない学生たちの困りごとが必ず出てくると思います。
実は、メンタルヘルスに不安のある学生や人間関係が不得手な学生、あるいは内部疾患や身体障害があって通学が大変だった学生の中には、オンラインの出席率は安定していた層もいたようです。そう考えると、このオンライン授業が学生にとって良かったのか良くなかったのか、まだ読み切れないところもあります。
そして今言われたように、オンライン授業や生活のあり方が多様化する一方で、身の振る舞いを単一化していくような力はすでに出てきていて、マスクをしろであるとか、大声でしゃべるなとか、ソーシャルディスタンスを保てとか……。でも、これらに馴染まない障害特性のある人もいるわけですよね。マスクをつけられなかったり、ずっと黙っていられなかったり、ソーシャルディスタンスみたいなものがとれなかったり。その人たちが社会的な制裁の対象になってしまうのではないか、新たなスティグマ性を負わされてしまうのではないかという懸念があります。だから両面を見ていかなければならないと思います。
支援のトリアージに陥らないために
――お二人の話をうかがっていて、障害者と障害者以外の困りごとを厳密に分けるのは難しいけれども、やっぱり異なる部分もあって、でもそこを突き詰めていくと、どちらを優先するかというお金やマンパワーの取り合いの話になって、結局トリアージの話に陥りそうになります。そのあたりをどう整理して考えればいいのでしょうか。
荒井 確かに支援や合理的配慮はマンパワーやお金を割くことでもあるので、資源の取り合いになれば敵対関係にもなりますし、教職員に多くのマンパワーが求められると、「これ以上は無理です」と言いたくなる気持ちは分ります。
これは養護学校義務化阻止闘争の歴史に学べる部分が多いのですが、普通校に行きたい障害児がいても、学校の先生はもう手一杯で受け入れは無理だと言う。でも障害児や障害児の親が言っているのは、まずはそこに「居させてほしい」ということでした。参加のあり方を多様化してくれたらなんとかなるんじゃないか、ということだったんです。
もちろんマンパワーやお金のパイを増やすことを訴えるのも必要な運動ではあるのですが、考え方や価値観を変えるだけで状況が大きく変わる場合もある。実際には価値観を変える方が難しいこともあるのですが……。
村田 これまでずっと思い続けていたことなのですが、障害を理解できるかどうかは経験の有無に依ると思うんです。その人自身やその人の文化をどうすれば理解できるようになるかと聞かれたら、まずは会わないとわからないよね、ということです。だから授業でもよく言うのですが、私の授業を90分間聞くより、障害のある人と30分でも話した方がよっぽど障害理解が進むよと。
荒井 有無を言わさず慣れが大事だというのはその通りで、かつて、青い芝の会注釈2の重度身体障害者たちがなぜ街に出ていったかというと、街の人たちを慣れさせるためだったと思います。
今となっては車いすの人を電車の中で見ても驚くことはないですが、それはただ単純に慣れたからではないでしょうか。
村田 これは極端なエピソードかもしれませんが、私には小学生の子どもがいるんですけど、最近は外国籍の子どもも増えているんですよね。それで学校で給食を食べるときに、みんなはお箸で食べるのですが、お箸を普段使わない子どもたちはフォークで食べるんです。これがもし日本人の障害のある子どもで、スプーンを使えたら少し楽になるという話だった場合、どうなるでしょうか。場合によっては合理的配慮のような交渉事が必要になるかもしれません。でもフォークを使う外国籍の子どもとなにが違うのでしょうか。手段の変更を許容するという意味では同じ話なので、周りが価値観や感覚をいかに変えていけるかが大切になります。
今、障害者運動から学ぶこと
――取材の中である支援者が言っていたのですが、支援が届かなかったと教員や支援者が思い悩んでいても、結局学生本人がどう思っているかがわからないと。支援が空回りしてるような感じすらあると表現されました。本人にもどうしたいのか、なにが必要なのかがわからない中、支援者はどう対応し、支援を構築していくべきなのでしょうか。
荒井 村田さんが冒頭(前編)で言われた相対的な気付きの話にも関わるのですが、かつての障害者運動は、自分たちの主体性をものすごく強く訴えていました。でも最近、主体性を重視する考え方に対して、ちょっと違うんじゃないかと言われてきていますよね。特に当事者研究の領域で言われていて、京都大学の油田さんが書かれた論文注釈3が非常におもしろかったのですが、「強い主体性」という言葉を使って、本当にそんなものがあるの?あるということでいいの?と問われています。例えば「自分のやりたいこと」ひとつとってみても、支援者との関係性や相性によって変わっていくものだと。
関係性の中での気付きって、相対的な気付きと同じことだと思います。いろんな人との何気ない関わりの中で、自分にとってベターな方向を選んでいく。そこからやりたいことが少しずつ出てくると。だから、関係性資源に恵まれている人は、自分がこれからなにをするのか、するべきなのかがあまり苦労せず見出せると思います。
一方で、障害者の中には、福祉の人とのつながりしかない人もいます。支援者も多くは福祉の人なわけですが、こうした人はなにも言わなくても助けてくれる。でもそれは、本当につながりと言って良いのだろうかと。それを問うことが70年代、80年代の障害者運動の大きなテーマだったと思うんですよ。つまり、福祉の人と付き合いたいわけじゃなくて、世の中と付き合いたいんだと。
世の中と付き合うために手助けが必要だから福祉の人が必要という発想だったのに、いつの間にか福祉の人が隣にいれば、その人との人間関係だけでなんとなく生活が回っているようにも見えてくる。でもそうじゃないだろうって思うわけです。そこからはみ出していく関係性が必要なんですよね。
大学という場所は、勉強する目的と同時に、ただ大学生であるというだけでいろんな人と出会い、人間関係をつくれる場でもあったはずです。それがこのコロナ禍で失われてしまったので、今後アフター・コロナの中でどう取り戻していけるかが、大学に問われていると思います。
村田 すごくわかります。この間、障害者運動から学ぶことがたくさんありました。今言われたように、福祉がほしいんじゃない、支援がほしいんじゃない、ただ生活をしたいんだっていう話は、大学でも同じことが言えますよね。別に支援がほしかったり誰かに助けてほしいわけじゃなくて、勉強がしたい、人と出会いたいということがまずあるはずだと。
私は支援部署で働いているので、これまでの障害者運動の経験をどう生かせるのか、これからも考えていきたいと思います。
2021年1月19日 Zoomにて収録
注釈2
日本脳性マヒ者協会青い芝の会
1957年に結成された脳性マヒ者たちを中心とする運動団体。日本における自立生活運動の始まりであったと言われる。青い芝の会の中心的存在、横田弘氏のことを書いた荒井裕樹氏の著書に『差別されてる自覚はあるか: 横田弘と青い芝の会「行動綱領」』(現代書館、2017)がある。
注釈3
油田優衣「強迫的・排他的な理想としての〈強い障害者像〉――介助者との関係における「私」の体験から」 →
#1にも登場する油田優衣さんが、高校を卒業し親元を離れ、介助者とともに初めて一人暮らしを経験する中で感じたり考えてきたことが論じられている。熊谷晋一郎編『当事者研究をはじめよう(臨床心理学増刊第11号)』(金剛出版、2019)所収。
荒井裕樹・あらいゆうき
1980年、東京都生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科修了。博士(文学)。二松学舎大学文学部准教授。専攻は、障害者文化論、日本近現代文学。著書に、『車椅子の横に立つ人 障害から見つめる「生きにくさ」』(青土社)、『障害者差別を問いなおす』(ちくま新書)、『差別されてる自覚はあるか 横田弘と青い芝の会「行動綱領」』(現代書館)、『生きていく絵 アートが人を〈癒す〉とき』(亜紀書房)、『隔離の文学 ハンセン病療養所の自己表現史』(書肆アルス)、『障害と文学「しののめ」から「青い芝の会」へ』(現代書館)などがある
村田淳・むらたじゅん
1981年、京都府生まれ。高等教育アクセシビリティプラットフォーム(HEAP)ディレクター、京都大学学生総合支援センター准教授、障害学生支援ルームチーフコーディネーター。2007年より、京都大学における障害学生支援に従事。組織的な支援体制の構築や合理的配慮の提供に関するシステムを構築する一方、支援現場で様々な取り組みを行う。全国高等教育障害学生支援協議会(AHEAD JAPAN)の理事など、対外的な活動も担いつつ、日々、大学における障害学生支援のコーディネーターとして従事する実践家。