相対的な気付きの喪失
――今回、荒井先生への取材依頼メールの返信に、先生たちが学生たちのSOSに気付きにくい状況が生まれていたと書いてあって非常に気になっていたのですが、この間、荒井先生から見た学生や大学の様子はどうだったのでしょうか。
荒井 まず私の所属している二松学舎大学は、東京都内にある大変小規模な私立大学です。たぶん小規模な大学だと似たところが多いと思うのですが、本学には障害学生に特化した支援部署があるわけではありません。メンタルヘルスに関わることや人間関係、それ以外にも様々な困りごとを、学生支援課と学生相談室が包括的に対応しています。教員ともわりと緊密に連携を取り合っているので、なんとなく私たちにも事情が伝わってきます。そうした大学の一教員の立場から見えてきた点をお話しします。
今回、最も大きかったと感じているのは、オンライン授業に移行したことで学生との「立ち話」がなくなったことです。小さな規模の大学ゆえに、平時であれば、日頃の雑談や立ち話、友達関係から聞こえてくる噂話の中で、困っている学生の存在をなんとなくキャッチできていたのですが、それが全然できなくなってしまった。本当につながれない学生が一部出てきてしまって、相談の潜在的な需要が掘り起こせなくなりました。
そもそも相談というのは、相談窓口に辿り着けたら半分ゴールしているようなものです。相談は自ら動かなければならない点で、実は非常に主体的な行為なんです。問題はむしろ、相談窓口に辿り着けない学生、相談できるということを知らずにいる学生をどうキャッチするかで、今回そうした学生との接点を失ってしまったことが非常に大きかったと感じています。
特に新入生ですよね。友達や先輩後輩などの人間関係のことを、私は「関係性資源」と言っているのですが、その資源を構築することができなかった。履修登録一つとっても、これまで友達や先輩を頼ってできていたことが、今年度は解説のYouTube動画を見ながら履修登録しているような状態でした。関係性資源という見えないインフラが切断されたところに、大きな問題を感じています。
実はオンライン移行で困りごとを抱えたのは、学生だけでなく教職員もでした。例えば、本校では学生との連絡にLiveCampusという情報プラットフォームを使っているのですが、授業課題の提示や回収でそのプラットフォームを使う教員もいれば、Googleのプラットフォームを使う教員もいたり、メールで提出を求める教員もいました。つまり、各教員がそれぞれ自分の使いやすい媒体を使ってしまうことで、学生たちは授業によって、様々なツールや媒体を駆使しなければならなかった。これは大変煩雑な作業で、強いストレスを覚える学生も少なくなかったようです。

村田 すごくよくわかります。このコロナ禍では、教職員も含めてみんな一斉に困ったということが生じたんですよね。仮にこれまでは、障害のある学生が困っている存在だとしたら、他の多くの学生は困っていない存在として、コントラストが明確にあった。ただ今回は全員が困ったので、別に障害者だけが困っているわけではなくなった。そうすると、障害ゆえの困りごとだからって大学側もそこばかりを気にできなくなって、障害学生もそれを感じ取って遠慮がちになってしまった。大変なのは自分だけじゃないと。
オンラインによって周りの姿が見えなくなったことの功罪は、本人が周りと比較して、自分と周りとの違いに気付けなくなったことではないでしょうか。周りの様子がわからないから、困っているのは自分だけじゃない、みんなも努力しているはずだから自分もなんとかしなきゃいけないと思うようになった。障害ゆえの困りごとすら内包してしまう状況があったのではないでしょうか。
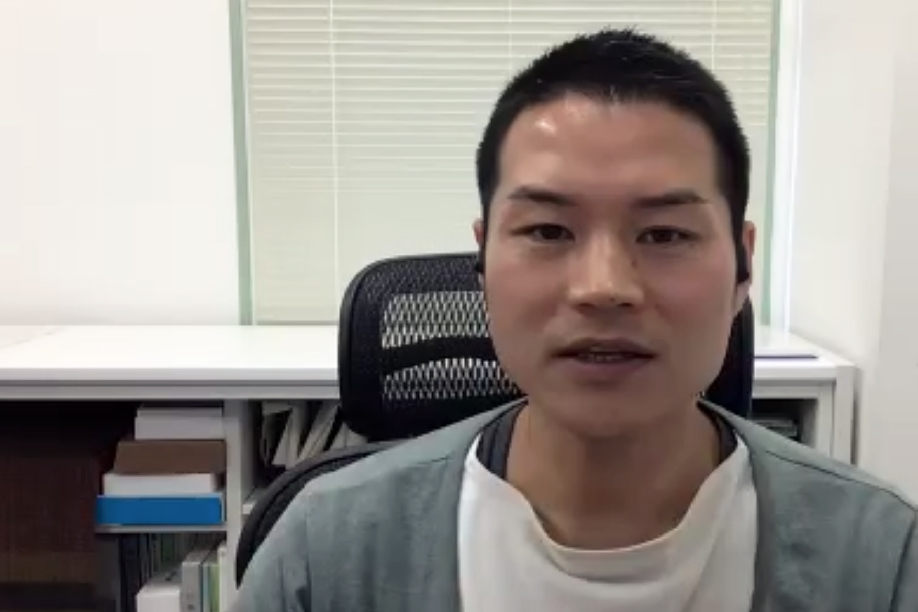
荒井 自分を相対化することで自分の困りごとが見えてくるというのは、確かにそうなんですよね。調査をしないとわからないですが、自分の困りごとに気付く機会を得られなかったために、特に注意欠陥があったり、切り替えが苦手な学生、あるいはメンタルヘルスに不安のある学生の中にはどうすればいいかわからなくなってしまった学生もいただろうな、と思います。
でも先ほども言ったように、そうした学生たちの様子が全然見えてこなくなったので、ほんとうにつながれない学生層が一部出てきてしまいました。
支援のトリアージが生まれていた
荒井 このコロナ禍では、障害学生のニーズが、周囲の学生の個別の問題に埋没してしまったように思います。私は障害者運動の歴史を調べている研究者でもあるので非常に言いにくいのですが、でも現実問題としてあったことで、私も一教員として「支援のトリアージ」みたいなことをやっていたかもしれません。
人がそれぞれ日常の暮らしを維持するのに必要な努力の量を、私は個人的に「生活負荷」と言っています。客観的なデータがあるわけではありませんが、このコロナ禍では、その生活負荷がかなり上がってしまったんじゃないか、そして、そこには格差も生じていたんじゃないか、と思うのです。
最近の学生は「実家が太い」という言い方をするのですが、実家が裕福だったり、家族との関係が良好な学生は、むしろオンライン移行で生活負荷が軽減されたかもしれません。例えばオンラインの授業を親御さんと一緒に見ているという学生もいたようです。親御さんも20年ぶりくらいに大学の授業を受けられると言ってすごく楽しんでいると。
一方で、自宅がむしろストレスフルな環境だという学生も少なくありませんし、経済的に困窮している学生が大変多いこともはっきり見えてきました。自分で生活費と学費を稼いでいて、中には週30時間を超えるアルバイトをしている学生もいるようです。飲食店でのアルバイトが多いので、働ける日数も減っていき、ますます経済的な困窮に拍車がかかってしまった。
学生たちは、私たち教員がイメージしているよりもっと困難な生活負荷を抱えながら生きています。各種調査でデータ的には判明していたものが、オンラインに移行して、個々の授業を運営する中で具体的な問題として現われてきた。先ほど、オンラインになって障害学生の潜在的な困りごとが見えにくくなったと言いましたが、これらは逆にオンラインになって「見えてしまった」ことです。
結果的に、障害のある学生たちのニーズや困りごとも、新たに見えてきた問題の後ろに押しやられ、埋没してしまう状況が生じてしまったのではないか。つまり、いろいろなところで「大変だ、大変だ」となったことで、障害のある学生だけに関心を向けられない状況が生まれたわけです。
そこで障害のある学生と障害のない学生との間で、困りごとの重さ比べのようなことが出てきかねないと思い、支援のトリアージという言葉を使いました。
村田 大学は学生に対して、これまで多くのことを暗に要請してきました。健康でなんの問題もなく、生活に困難があっても平気な顔をして教室に現れることを期待していた。
でも今回、生活と学習の距離が著しく近くなったことで、これまで教室には頑張って行ってたかもしれないけれど、家の中には本人の頑張りではどうにもならない生活実態が入り込んでしまった。今まで見えていなかったことが問題としてたくさん出てきたので、教員も職員もどう対処すべきかがわからなくて、無意識に支援のトリアージみたいなことをしてしまっていたのかもしれません。
荒井 ただもちろん、障害学生のニーズが埋没しないように、支援のトリアージみたいなものが肯定されないようなあり方を考えていかなければなりません。
こうしたトリアージという言葉や、最近では優生思想という言葉もよく聞かれるようになりましたが、これほどメディアに出てくるとは思いもしなかったので、非常に恐ろしく感じています。
そもそも、言葉の使われ方がずいぶんと変わってきています。優生思想という言葉は、さかのぼると70年代の障害者運動の中で盛んに使われた用語で、「健全者幻想」と対になって使われることが多かったんです。健全者が障害者よりも上の立場にあって、上から目線で障害者を見下す際の価値観を優生思想と言っていました。
最近の使い方では、みんな苦しく困っている中で、「なんだよあいつ、俺より役に立っていないのに……」と、内輪で自分よりさらに下にいる人を見つけ出そうとする感覚や感情を、優生思想と呼び始めているような節があります。
支援のトリアージと優生思想は別物だとは思いますが、同じ困っている者の中で優先すべき者と後回しにする者といった区別が肯定されていけば、優生思想につながりかねないと思います。
障害者運動の歴史って「後回しにするな」という運動で、「今みんな大変なんだからちょっと黙っててくれ」とか、「みんな大変なんだから施設に入ってくれ」ということに反対する運動だったわけです。
――経済や家庭の事情で退学を考えざるを得なかったり、授業を受け難くなっている状況は、個々の学生にとっては非常に切実な問題です。ただそこで、障害のある学生とどちらが大変かを比べざるを得ないのは、全体的な余裕のなさが背景にあるように思います。もう少し具体的に、どのような状況があったか教えていただけるでしょうか。
荒井 オンライン授業になって、注意欠陥や発達障害のある学生が、課題の管理や情報ツールの切り替えに対応できなかったりする。自宅の通信環境が整っていない学生もいる。あるいは家族や同居人との関係で自宅での受講が難しい学生もいました。ほかにも、友人との関係性が途切れて苦しむ学生や、オンラインでのコミュニケーションに強いストレスを覚える学生もいました。そして教員の方もオンライン授業で負担が倍増して、ギリギリのところでやっている。そのような中で、どこから手をつけ解決していくのかという問題です。
自分のパソコンをもっていなかったり、経済的な事情で安定的な通信環境を得られない学生たちもいて、大学側も対策を講じましたが、それでも受講が困難な学生もいて、出席や課題に配慮・対応して欲しいといった要望が出て来たりしたわけです。
いろいろな学生たちが、いろいろなSOSを発してくる中で、教員としてどう対応するか、何ができるのかを毎日考えなければなりませんでした。学生が直面している困りごとが、メンタルヘルスや発達障害によるものなのか、経済事情によるのか、家庭環境によるのか、情報通信機器のスキルによるのか、こちらからは区別が難しい。いろいろな学生の困りごとが積み重なり、全ての問題には対応し切れない中、どうしても一部の障害学生への対応を分けて考えることが難しくなってしまったように思います。
後編につづく
荒井裕樹・あらいゆうき
1980年、東京都生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科修了。博士(文学)。二松学舎大学文学部准教授。専攻は、障害者文化論、日本近現代文学。著書に、『車椅子の横に立つ人 障害から見つめる「生きにくさ」』(青土社)、『障害者差別を問いなおす』(ちくま新書)、『差別されてる自覚はあるか 横田弘と青い芝の会「行動綱領」』(現代書館)、『生きていく絵 アートが人を〈癒す〉とき』(亜紀書房)、『隔離の文学 ハンセン病療養所の自己表現史』(書肆アルス)、『障害と文学「しののめ」から「青い芝の会」へ』(現代書館)などがある
村田淳・むらたじゅん
1981年、京都府生まれ。高等教育アクセシビリティプラットフォーム(HEAP)ディレクター、京都大学学生総合支援センター准教授、障害学生支援ルームチーフコーディネーター。2007年より、京都大学における障害学生支援に従事。組織的な支援体制の構築や合理的配慮の提供に関するシステムを構築する一方、支援現場で様々な取り組みを行う。全国高等教育障害学生支援協議会(AHEAD JAPAN)の理事など、対外的な活動も担いつつ、日々、大学における障害学生支援のコーディネーターとして従事する実践家。